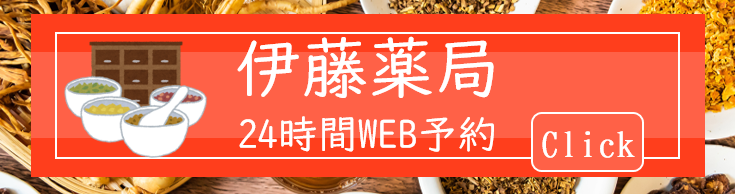ブログ
七夕と小暑。夏の養生の基本は「不正去邪」
今日は七夕。
織姫と彦星のお話は誰もが知るところですが
七夕は奈良時代に中国から日本に伝わりました。
古代中国には、「五節句」と呼ばれる暦があり
七夕もこの一つ。
節句というと日本では
桃の節句、端午の節句がポピュラーですが本来は7つあり
七夕は「七夕(しちせき)の節句」
と呼ばれてます。

五節句は、季節の節目の宮中行事として
邪気を払ったりお祝いをするなどしていました。
「人日の節句」以外は全部ゾロ目の日なんですね~。
==========
人日(じんじつ) 1月7日=七草。1年の無病息災を祈る日
上巳(じょうし) 3月3日=桃。桃で邪気を払う日
端午(たんご) 5月5日=菖蒲。男の子の成長を祈る日
七夕(しちせき) 7月7日=竹。縫物などの芸事の上達を願う日
重陽(じゅうよう)9月9日=菊。陽が最盛になって重なる日
==========
このように、時代と共に農民にとっても
季節の節目に安寧を祈って祭りをする
大切な行事になっていったようです。
また、今年は
今日が二十四節気の「小暑」。
梅雨明けしてこれから本格的に暑さも増してくる時期になりました。
暑気あたりや熱中症などの症状も出やすくなりますが
暑さの対策はしっかりと出来ていますか?
中国の古典の医学書である「黄帝内経(こうていだいけい)」には
夏のの養生方法の注意する点として
「太陽を避けるようなことをしてはいけない」
と書かれています。
これは、暑さに応じて体を慣らすことも大切、ということを
意味しますが、今の日本は屋外はうだるような暑さでも
屋内に入ると冷房の効いた涼しい部屋で過ごすため
体温調節が難しく、自律神経のバランスに乱れたりしがち。
熱中症予防にこまめな水分補給はしていても
つい暑いと口に入れるものは冷たいものばかりになったり
涼しい部屋で過ごしがちになります。
夏バテしない体づくりのためにも
体内から元気や気力を養うことで
暑さにも対応できる体作りが肝心です。
基礎体力をつけるためにも
食事は基本温かいものか常温で食べるようにしましょう。
加熱しても食材の効能によって、体内にこもりがちな
余分な熱を取り除くことが出来ます。
小麦、瓜類、レタス、トマト、豆腐、こんにゃくなどは
寒涼性なので、積極的に摂るのがおすすめです。
水分補給はただ水を飲むだけではなく
体内を潤す作用のある食材を摂ることで渇きを予防できます。
特におすすめなのはスイカやメロン。
体液を増やしたり、利尿作用によって余分な熱も排出します。
冷やす作用が強いので、あまり冷やさずにできれば常温で
食べるようにしてください。
冷えやすい場合は、多食しないようにするか、
温性の桃を食べるといいですよ。
アイスクリームやかき氷が食べたくなりますが
回数を減らして、自然の物を取り入れることで
予防や軽い症状の緩和であれば食材でも十分に出来ます!!
自然の力に勝るものはありません。
食材の効能を取り入れながら暑い夏を乗り切りましょう!
執筆:国際薬膳師 清水柚紀子
織姫と彦星のお話は誰もが知るところですが
七夕は奈良時代に中国から日本に伝わりました。
古代中国には、「五節句」と呼ばれる暦があり
七夕もこの一つ。
節句というと日本では
桃の節句、端午の節句がポピュラーですが本来は7つあり
七夕は「七夕(しちせき)の節句」
と呼ばれてます。

五節句は、季節の節目の宮中行事として
邪気を払ったりお祝いをするなどしていました。
「人日の節句」以外は全部ゾロ目の日なんですね~。
==========
人日(じんじつ) 1月7日=七草。1年の無病息災を祈る日
上巳(じょうし) 3月3日=桃。桃で邪気を払う日
端午(たんご) 5月5日=菖蒲。男の子の成長を祈る日
七夕(しちせき) 7月7日=竹。縫物などの芸事の上達を願う日
重陽(じゅうよう)9月9日=菊。陽が最盛になって重なる日
==========
このように、時代と共に農民にとっても
季節の節目に安寧を祈って祭りをする
大切な行事になっていったようです。
また、今年は
今日が二十四節気の「小暑」。
梅雨明けしてこれから本格的に暑さも増してくる時期になりました。
暑気あたりや熱中症などの症状も出やすくなりますが
暑さの対策はしっかりと出来ていますか?
中国の古典の医学書である「黄帝内経(こうていだいけい)」には
夏のの養生方法の注意する点として
「太陽を避けるようなことをしてはいけない」
と書かれています。
これは、暑さに応じて体を慣らすことも大切、ということを
意味しますが、今の日本は屋外はうだるような暑さでも
屋内に入ると冷房の効いた涼しい部屋で過ごすため
体温調節が難しく、自律神経のバランスに乱れたりしがち。
熱中症予防にこまめな水分補給はしていても
つい暑いと口に入れるものは冷たいものばかりになったり
涼しい部屋で過ごしがちになります。
夏バテしない体づくりのためにも
体内から元気や気力を養うことで
暑さにも対応できる体作りが肝心です。
基礎体力をつけるためにも
食事は基本温かいものか常温で食べるようにしましょう。
加熱しても食材の効能によって、体内にこもりがちな
余分な熱を取り除くことが出来ます。
小麦、瓜類、レタス、トマト、豆腐、こんにゃくなどは
寒涼性なので、積極的に摂るのがおすすめです。
水分補給はただ水を飲むだけではなく
体内を潤す作用のある食材を摂ることで渇きを予防できます。
特におすすめなのはスイカやメロン。
体液を増やしたり、利尿作用によって余分な熱も排出します。
冷やす作用が強いので、あまり冷やさずにできれば常温で
食べるようにしてください。
冷えやすい場合は、多食しないようにするか、
温性の桃を食べるといいですよ。
アイスクリームやかき氷が食べたくなりますが
回数を減らして、自然の物を取り入れることで
予防や軽い症状の緩和であれば食材でも十分に出来ます!!
自然の力に勝るものはありません。
食材の効能を取り入れながら暑い夏を乗り切りましょう!
執筆:国際薬膳師 清水柚紀子
Archive
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2019年9月